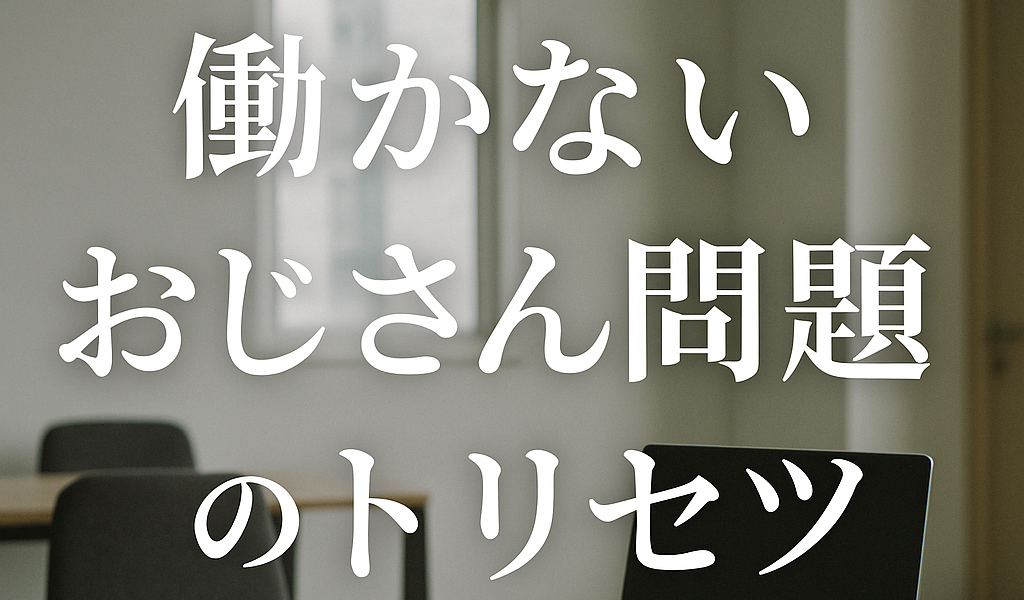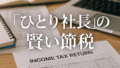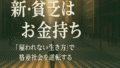【要約・感想】「働かないおじさん問題」のトリセツ|職場の不公平とムダの構造を変える実践書
導入:どの職場にもいる「働かないおじさん」——放置していませんか?
こんにちは、知識で稼ぐ読書部屋へようこそ。ちかどろです!
今回紹介するのは、組織に潜む厄介な問題「働かないおじさん」を真正面から取り上げた一冊、
『「働かないおじさん問題」のトリセツ』(難波猛 著)です。
年功序列で役職に就きながらも、現場では何もしない・動かない・責任を取らない…。
そんな中高年社員の存在に、若手がやる気を失ってしまうという声は少なくありません。
本書は、この問題の根本構造にメスを入れ、現場でできる対策まで提案する実践的な書籍です。
書籍概要
- 書名:「働かないおじさん問題」のトリセツ
- 著者:難波 猛
- 出版社:アスコム
- 発売日:2021年9月18日
- ページ数:312ページ
- ISBN:978-4776211488
要約:なぜ「働かないおじさん」が生まれるのか? 3つの構造要因
1. 年功序列と成果主義のミスマッチ
企業内でよくあるのが、年齢と役職が上がったのに、仕事の中身はそのまま、あるいは減っていくという状況です。
一方で成果主義を導入しているにもかかわらず、評価の対象外にされていたり、温情人事で処遇されていたりする現実も。
この「制度と実態のねじれ」が、“働かない”状態を温存してしまうのです。
2. 組織の“空気”と放置文化
「もうあの人には期待していない」「言っても変わらないから…」
そんなあきらめの空気が蔓延している組織では、“おじさん問題”はさらに深刻化します。
職場全体の生産性が落ち、若手やミドル層のモチベーションにも悪影響を与えます。
3. 当人の「やる気」がなくなる環境
当の“おじさん”たちも、最初から働かないつもりだったわけではありません。
過去の評価、無理な配置転換、やりがいの喪失などが積み重なり、「もうどうでもいい」となっているケースも。
この悪循環が「働かない状態」を固定化させてしまうのです。
著者の提案:「働かないおじさん」を動かす処方箋
- 組織全体:年功的処遇からスキルベース評価への転換
- 管理職:「放置」ではなく「役割の再定義」で対話を促す
- 本人:キャリアの棚卸しとリスキリングで再起を図る
著者は一貫して「おじさんも再び輝ける」ことを前提に書いています。
「排除」ではなく「活用」の視点でのマネジメントは、これからの組織に不可欠だと感じました。
読後の感想:見て見ぬふりをやめたくなる一冊
正直、「あの人、いるだけで何もしてないな…」と思った経験、私にもあります。
でもこの本を読んでからは、「なぜそうなっているのか?」と背景に目を向けるようになりました。
単に批判するのではなく、対話と再設計で職場を変えていこうという提案に、強く共感しました。
若手の不満だけでなく、ミドル・シニア層の再挑戦も応援する姿勢が印象的です。
活用法・メリット:職場改革の第一歩に
- 評価制度の見直しや、人材配置の参考にできる
- ミドル層の活用やリスキリングのヒントが得られる
- チームマネジメントや1on1ミーティングの改善につながる
- 部下・上司それぞれの立場からも読みやすい構成
まとめ:「働かないおじさん問題」は職場の未来を考えるチャンス
『「働かないおじさん問題」のトリセツ』は、「職場にありがちな困った存在」にどう向き合うかを、極めて実践的に教えてくれる一冊です。
問題を放置せず、変えていく姿勢があるかどうかで、組織の未来は大きく変わる。
今まさに職場の停滞感を感じている方にこそ、読んでいただきたいと思います。